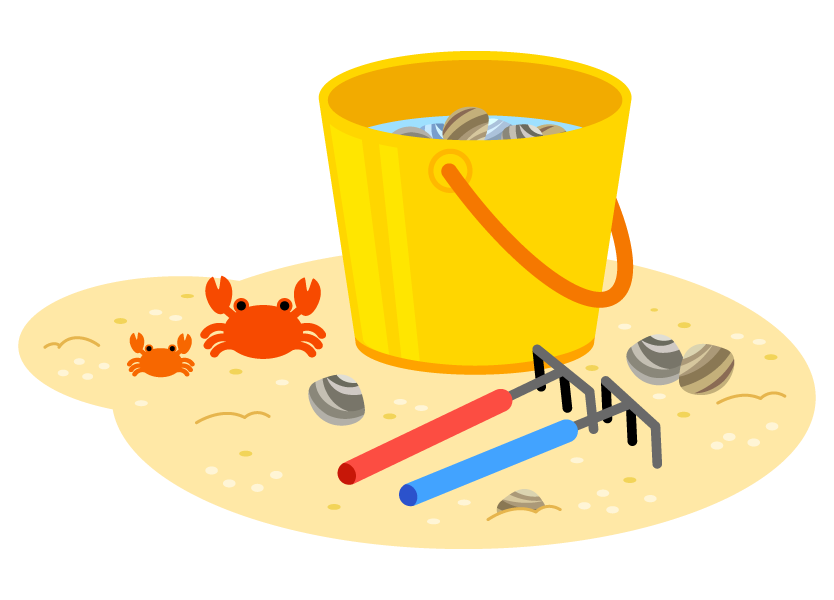天気の良い日、親子で潮干狩りに繰り出して一生懸命貝を採っているとき、ふと子供に「この貝って何?」と聞かれたとき、スマートにすらすら答えられたら父親としての株も上がると思いませんか。
ということで、親子連れで潮干狩りに行くお父さんに知っておいていただきたい貝の見分け方と注意したい貝の毒について紹介します。
スポンサーリンク
潮干狩りでとれる貝の種類は?
潮干狩りで採れる貝の種類はいくつかありますがその中でも代表的なものを紹介しますね。
- アサリ
潮干狩りの一等メジャーな貝ですね。味噌汁にしても酒蒸しにしてもおいしいです。旨みがあり、調理用途が広いですね。 - ハマグリ
お吸い物や網焼きなどで有名ですね。
しかし、潮干狩りでとれるハマグリはほぼ「チョウセンハマグリ」か外国産の「シナハマグリ」です。
昔は日本でも国内産のハマグリが取れたものですが、現在ではレッドリストの絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。 - オキシジミ
その名の通りシジミに似た貝です。
シジミよりかなり大きくなります。
調理方法はしじみと同じで味噌汁などです。 - ホンビノス
外来種であり、「大アサリ」「白ハマグリ」と呼ばれることもあります。
結構いい出汁が出るためクラムチャウダーなどで使われます。 - バカガイ(アオヤギ)
なんだかすごい名前をしていますが、とっても美味しい貝です。
寿司ネタで言う青柳と同じです。
寿司や刺身、天ぷらに使われます。 - シオフキガイ
あさりよりも多く取れることがある貝です。
あさりと同じ調理もできますが、砂抜きが若干難しいです。
潮干狩りでとれる会の見分け方
取れる貝の見分け方
こちらのサイトに写真が載っているので分かりやすいです。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n62052
スポンサーリンク
- アサリ
4cmくらい
放射線状に細い筋がたくさんあり、個体によって貝の模様が様々です。 - ハマグリ
8cmくらい
表面が滑らかで丸みがあり、黄褐色に褐色や紫色で模様が多彩です。 - オキシジミ
5cmくらい
円形のものが多く、殻は良く膨らんでいる。 - ホンビノス
10cmくらい
殻は白く、円形だが大きくなるにつれて少し殻長が長くなる。 - バカガイ(アオヤギ)
10cmくらい
全体的に茶色で放射線状の筋が特徴。 - シオフキガイ
4cmくらい
アサリとよく間違えられます。
薄紫形の色が多いがあまり目立つ特徴がなく、ふっくらしています。
潮干狩り注意したい貝毒とは?
アサリや、シオフキガイといった潮干狩りで採れる貝類について注意したいのが貝毒です。
貝毒とは?
二枚貝は、プランクトンを食用としていますが、毒を持つ事があります。
原因は、餌となるプランクトンが有毒だったことです。
有毒プランクトンを食べると、貝の内部に蓄積されより強い毒素となります。
一度毒素を取り込んだ貝は、有毒プランクトンがいないところでしばらく育てると、毒素が抜けて無毒に戻ります。
貝毒の強さ
毒貸した貝を誤って食べてしまうと、下痢・嘔吐・麻痺などの食中毒症状を引き起こします。
麻痺性貝毒と下痢性貝毒があります。
麻痺性貝毒はふぐ毒にも匹敵する強さで、命にかかわることがあります。
毒があるかについては、管理している所に聞くのことが一番確実です。
関連記事:潮干狩りの場所は千葉?木更津のおすすめスポットと有料無料のメリット・デメリット
まとめ
どうでしたか?
楽しい潮干狩りの計画を立てるためにもきっちり予習しておきましょうね。
スポンサーリンク